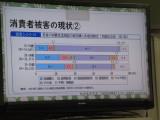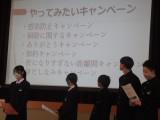平成28年施設隣接型小中一貫校「前芝学校」開校。本年度で10年目となります。
行事・日々の様子(R7)
3年生の委員会が最終となりました。
2月19日(木)今日は3年生最後の委員会でした。委員会の最後には、3年生から後輩に向けてメッセージが贈られました。委員会によっては、3年生のメッセージを受けて自分たちがどんなことをがんばっていきたいかを伝えていました。
前芝中学校がさらによくなるように、どの生徒も思いをもってくれていて、とても温かい気持ちになりました。
3年生を送る会が近づいてきました。
2月19日(木)の5時間目は、1・2年生が、役割やグループに分かれて3年生を送る会の準備をしていました。それぞれの得意分野を生かしていて、絵が好きな子は絵を描いたり、もの作りが好きな子は小道具を作ったり、歌やコントが上手な子はその練習をしたり、企画をするのが上手な子は考えたことをみんなに指示したりなどしていて、それがとてもいいなあと思いました。また、前回も書きましたが、本当にこういう時の子どもたちの表情は生き生きとしています。先生に言われなくても、どんどん自分たちで意見を出し合い、3年生に喜んでもらえるように工夫を重ねています。この表情を授業でもたくさん見られるように、教員はもっともっと授業力を高めていきたいです。
3年生の美術の授業もいよいよ最終となりました。
2月18日(水)の6時間目は3年生にとって最後の美術の授業でした。まずはポップアップカードの作品交流を行いました。その後、教科担任の先生から最後のメッセージをいただきました。生活の中の美術、美術と他教科との関連性、今後の人生における美術とのかかわりなども含めて、心温まるメッセージと今後へのエールをいただきました。最後に、今回も子どもたちからの手紙を教科係の生徒から手渡し、最後に拍手で感謝の気持ちを伝えました。
1年生の美術作品を紹介します。
1年生の美術では、美術の「美」という文字を、自分が美しいと思うものをイメージして自分なりにデザインしました。それぞれ個性あふれる楽しい作品で、美しいと思うものも人それぞれで、自然、宇宙、桜、花火などなど、一つとして同じ作品はありませんでした。中にはお金を選んだ生徒もいました。
世界に一つだけの美しいものを詰め込んだ「美」が完成しました。
篆(てん)刻づくりに取り組んでいます。(2年美術)
2年生の美術では、ふだんの授業とは打って変わって、真剣な表情で篆(てん)刻づくりに取り組んでいました。印面には自分の名前をデザインし、持ち手のデザインも自分で考えるそうです。ほとんどの生徒が印面を篆刻刀で彫り進めていました。文字自体を彫るのが陰刻(横から見た形が凹)、文字以外の部分を彫るのが陽刻(横から見た形が凸)といい、生徒たちは自分の好みに合わせて彫り方を選択します。細かな作業に集中して取り組む様子に、教材の価値を感じました。
1年生の技術、2年生の家庭科の授業を紹介します。
2月17日(火)今日は1年技術、2年家庭の授業の様子を紹介します。
1年生の技術では、文字をデジタル化する学習を行っていました。デジタル化した文字を友達に伝え、その文字を当てることをしていました。また、ピクセルや画素について、数字が増えれば増えるほどより鮮明に、よりクリアになっていくことを実際の映像やゲームで確認していました。難しいそうですが、子どもたちにとってはかなり身近なことだったようで、一人一人が興味をもって学習に取り組んでいました。
2年生の家庭科では、消費者被害について学んでいました。被害の具体的な内容、被害にあいやすい場面や年齢などについて学びました。実際の被害について、ロールプレイング(役割演技)をすることにより、さらに理解を深めていました。役者ぞろいの2年生なので大いに盛り上がっていたそうです。参観に行ったときはすでに終わっていたのですが、サービスでもう1回心優しい生徒たちが怪しい(!?)芸能事務所の勧誘のロールプレイを見せてくれました。
3年生は最後の授業で・・・。
卒業式はまだ少し先ですが、3年生は最後の授業となる教科が少しずつ出てきました。2月16日(月)は最後の音楽の授業、17日(火)は最後の家庭科の授業でした。授業の最後にクラス全員からの手紙を教科係が渡し、全員で「ありがとうございました」という言葉と感謝の拍手を送りました。先生がたからもメッセージをいただきました。技術は先週終わってしまったので、今日、無事に手紙を渡すことができました。
3年生も学校へ来るのはあと12日です。寂しい気持ちが増してきます。
整美・ボランティア委員会とボランティアの皆さんでワックスがけを行いました。
2月16日(月)の授業後にワックスがけを行いました。整美・ボランティア委員会が中心となって、ボランティアを全校に呼びかけ、教室・学習室・音楽室・保健室のワックスがけを行ってくれました。ボランティアも1年生4名、2年生8名、3年生5名の17名が参加してくれました。受験を控えた3年生も参加してくれたことを本当にうれしく思います。今年の3年生は、最後の最後まであいさつ運動にも多くの生徒が参加してくれました。きっと今の2年生がその素敵な伝統を引き継いでくれると思います。
日中は暖かかったのですが、夕方には気温も低くなり、急に冷え込みました。水はとても冷たかったのですが、ワックスがついたモップをきれいになるまで我慢して洗ってくれました。自分にできることを見つけて率先して動いている人もたくさんいました。
整美・ボランティア委員会の皆さん、ボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。
保健だよりで1月の生活チェックの結果をお知らせしました。
2月13日(金)に保健だより第18号を配付させていただきました。中学生になるとなかなかプリントが家に届かないという話を聞きます。重要なものはメールで配信させていただいておりますが、保健だよりも子どもたちの健康を守る重要なおたよりですので、今回も読んでいただきたいという思いでデータをPDFで貼り付けさせていただきます。
2月2日から3月2日までの1か月間、私のメディチャレ宣言に基づき、努力をしている最中ですが、毎日できている人とできていない人の両極端な状況が生まれています。
冬休み明けの生活チェックの平均点も9月より下がっています。特に低いのはやはりメディアの使用時間です。『メディアの使用時間が増える→学習時間が確保できない・就寝時刻が遅くなる→朝起きられない』 この悪循環を断ち切るには、やはりメディアの使用時間を減らすこと以外にはありません。メディチャレも後半戦に突入しました。残り2週間で良い習慣を身につけてほしいです。
こちらをご覧ください。 保健だよりR8.2.13 第18号 (生活チェック).pdf
★前芝中の玄関前はいつも季節を感じさせてくれます。生徒や先生がたの作品です。
全校集会がありました。
2月13日(金)の学期末テスト終了後の3時間目に全校集会を行いました。
はじめに、整美ボランティア委員会のクリーンロッカーキャンペーンの表彰を行いました。1位は3年1組、2位は2年1組でした。続いて、テニスの大会、防火ポスター、校内スペリングコンテスト(1・2年)の表彰を行いました。
今日の全校集会では、生徒会執行部企画による今年一年間の振り返りを行いました。運動会やフェスタ前芝、百人一首大会、全校レクレーションなどの行事について〇✕クイズの形式で問題を出し、全校で楽しく思い出を振り返ることができました。また、正解発表後には、その行事で活躍した3年生にインタビューを行い、3年生の出番も作ってくれて、全校最後の思い出がまた一つ増えました。
生徒会執行部の皆さん、いつも楽しい全校集会を企画してくれてありがとうございます。そして、それを目いっぱい楽しむことのできる前芝中学校の皆さんもありがとうございます。
1・2年生はテスト週間も終わり、今日から部活動も再開です。今週末は、テニス部がとよしん杯に出場します。がんばってほしいですね。今週からA日課(50分授業)が始まります。19日(木)は3年生にとって最後の委員会になります。後輩へ今年もメッセージを送ってくれると思います。メディチャレも継続しています。まずは1か月、がんばりましょう!!
ずいぶん暖かくなりましたが、まだまだ体調管理が大切な時期です。感染症対策は自分自身でもしっかり心がけるようにしましょう。
愛知県豊橋市前芝町塩見1
TEL:0532-31-0507
FAX:0532-34-1681
Mail:maeshiba-j@toyohashi.ed.jp
こちらのQRコードからもご覧
いただけます。

【愛知県教育委員会公式X(旧Twitter)のお知らせ】
愛知県教育委員会では、公式X(旧Twitter)を運用しております。
県の教育施設やイベント情報等を随時発信しますので、ぜひご覧ください。
アカウント名
愛知県教育委員会@aichi_kyoiku